「親が亡くなって実家が空き家になったけれど、遠方に住んでいて管理ができない」「親の家をどうするか決められず、そのまま放置してしまっている」
こうした悩みを抱える方が、近年増えています。
この記事では、「親の家を管理できないからどうするのが最適か?」というお悩みを持つ方向けに、放置によって生じるリスクや、現実的な選択肢、そして具体的な解決方法について解説します。
親の家を管理せず放置していると何が起きるのか?
相続後に誰も住まない親の家を放置すると、さまざまな問題が発生します。
まず最も多いのが、建物の老朽化です。人が住んでいない家は傷みが早く、雨漏り・カビ・害虫の発生などが進行します。加えて、以下のようなトラブルの温床にもなります。
- 草木が伸びて近隣に迷惑をかける
- 不審者や不法投棄の対象になる
- 火災や倒壊の危険性が高まる
- 固定資産税など維持費だけが発生し続ける
近所の人から苦情が来たり、行政から「管理不全空き家」に指定されることもあり得ます。そうなると「特定空き家」として、税の優遇措置がなくなり、固定資産税が4倍程度になる可能性があります。
仮にそうはならなくても、フェンスやブロック塀の倒壊、雨樋の破損などで、暴風時に近隣住民へ迷惑をかけてしまったり、通行人を怪我させてしまうリスクをはらむことになります。
もしも建物や人を傷つけてしまったら賠償問題に発展するでしょう。
親の家の管理が難しい理由とは?
「管理したいけどできない」人には、いくつかの共通した事情があります。
- 現在の自宅から遠方にあり、頻繁に行けない
- 忙しくて時間が取れない
- 他の相続人と連絡が取れず、処分の話が進まない
- 感情的に手をつける気になれない(思い出が多い)
- どう処分すべきか情報がなく、判断できない
これらの問題は一人で抱え込むとさらに長期化します。まずは“現状を知ること”が第一歩です。
一時的な対処法:どうしても今すぐ決められない人へ
親の家を管理できないならば、家を売却するか、解体して更地にして土地を売却するしかありません。
どうしてもすぐに売却や解体の判断ができない場合は、一時的に家を管理する方法も検討できます。
たとえば、空き家管理サービスを使えば、月額5,000円〜で定期的に通風・清掃・草刈りを代行してくれる業者があります。また、シルバー人材センターや地域のNPO団体が安価で管理業務を請け負ってくれるケースも。
一時しのぎであっても「完全放置」に比べれば、家の資産価値や周囲への印象は大きく違ってきますね。
管理できない親の家をどうするか?3つの選択肢
家をどうするかを決めるには、以下の3つの選択肢があります。
- 売却する
- 賃貸に出す
- 解体して更地にする
どの選択肢が最適かは、家の状態・立地・築年数・市場ニーズなどによって変わります。ポイントは、「売るか、貸すか、壊すか」を感覚や印象ではなく、“数字で判断”することです。
家の価値を知れば、次の一手が見える
売却するか、賃貸に出すか、あるいは解体するか。その判断基準となるのが「今の家の価値」です。
査定を受ければ、どの選択肢が費用的にも合理的かが見えてきます。
特に、地方や築古の家などは「値段がつかないのでは」と思い込んで放置しているケースも多いですが、近年では「古家付き土地」として需要がある地域も増えています。
感情面で手が付けられない人へ
「片付けられない」「遺品が多すぎて手がつかない」という感情的なハードルを抱えている人も少なくありません。
こうした場合、遺品整理の専門業者に依頼するという選択肢もあります。費用の目安は、1LDKで10万〜20万円程度。プロの手で丁寧に仕分け・処分してもらえるため、気持ちの整理にもつながります。
また、「思い出は残したいけれど、前に進まないといけない」と感じているなら、一部を写真に残したり、形見分けを済ませることで、気持ちの整理をつける方も多いです。
親の家の管理に関するよくある質問(FAQ)
Q:兄弟と話し合いができていないが売れる?
A:相続人全員の合意が必要です。ただし、話し合いのサポートをしてくれる不動産会社や専門家に相談することでスムーズに進む場合もあります。
Q:築50年の家、価値はゼロ?
A:建物自体の価値は低くても、「古家付き土地」として取引されるケースがあります。まずは査定で市場価値を確認しましょう。
Q:住んでいないのに火災保険って必要?
A:空き家でも火災や自然災害のリスクはあるため、空き家用の火災保険に加入するのが望ましいです。
イエウールで今すぐ無料査定してみる
全国の不動産会社に一括で査定依頼できる『イエウール』を使えば、たった1分の入力で複数社から見積もりが届きます。
相続した家の管理に悩んでいるなら、まずは「どれくらいの価値があるのか」を知ることから始めましょう。
管理できないままズルズルと時間が経つと、問題は大きくなっていきます。今こそ、“決断のタイミング”かもしれません。
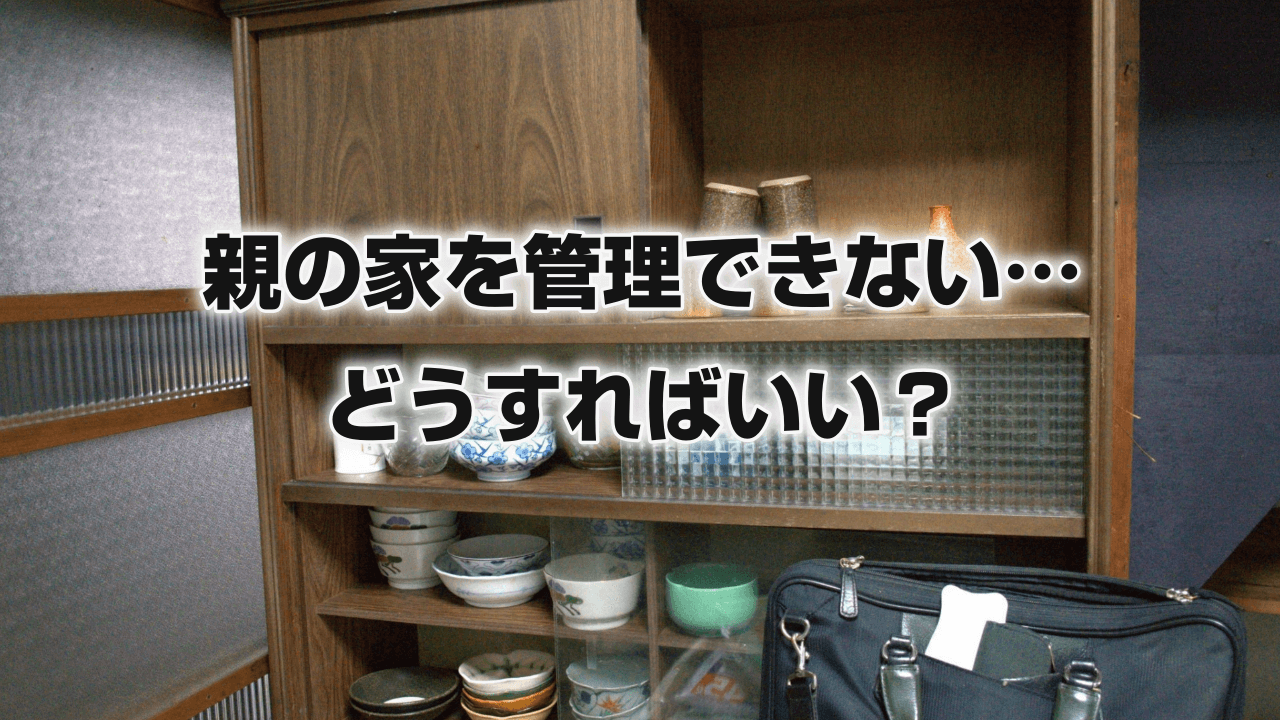


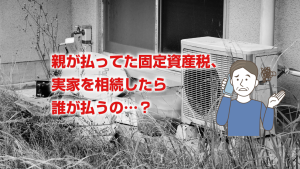



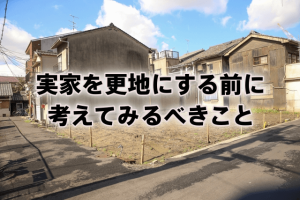
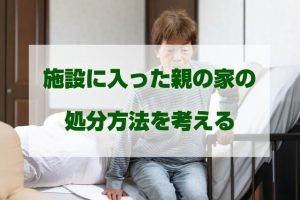


コメント