「お墓を整理したいけど費用が心配」「墓じまいを考えているけれど、金銭的な負担がネックになっている」
そんな方にぜひ知っておいてほしいのが、各自治体が独自に設けている“墓じまいの補助金”です。
近年、少子高齢化や都市部への人口流出によって、地方にある実家やお墓の管理が難しくなるケースが増えています。それに伴い、墓じまいをする人も増えていますが、経済的な理由で先延ばしにしている方も少なくありません。
そこで、この記事では「墓じまい 補助金」という観点から、具体的な補助制度や申請の流れについて詳しく紹介します。
墓じまい費用の詳細は別記事で
墓じまいにかかる費用の内訳や目安については、以下の記事で詳しく解説しています。費用感を把握したい方は、ぜひこちらも参考にしてください。

この記事では「補助金」に特化して、実際に利用できる制度とその活用方法をご紹介します。
墓じまいで利用できる主な補助金制度
墓じまいの補助金は、国が一律で設けているものではなく、主に地方自治体や市町村単位で実施されています。内容や金額、条件などは地域によって大きく異なりますが、ここでは代表的な例を紹介します。
秋田県鹿角市「墓地整理支援事業補助金」
- 補助金名:墓地整理支援事業補助金
- 補助額:最大5万円(改葬・墓石撤去にかかる費用の2分の1を上限)
- 条件:市内にある無縁化のおそれがある墓地を撤去し、改葬または永代供養にする場合
- 注意点:事前申請が必要。工事前に承認を得ていないと補助対象にならない。
福井県越前市「墓じまい支援事業補助金」
- 補助金名:墓じまい支援事業補助金
- 補助額:1件あたり最大10万円(実費の2分の1を上限)
- 条件:越前市内にある墓地を墓じまいし、市が指定する方法で改葬すること
- 申請期限:毎年4月〜翌年2月末(予算上限に達し次第締切)
長野県木曽町「改葬支援補助金」
- 補助金名:改葬支援補助金
- 補助額:最大8万円
- 条件:町内にある墓地を改葬し、町内の共同墓や納骨堂に移すこと
- 注意点:業者の見積書・施工前写真・使用許可証などが必要
その他、過疎地域では導入事例多数
北海道、山形県、島根県、熊本県などの過疎地域や高齢化が進む自治体では、同様の補助金制度を独自に展開していることがあります。
各自治体の補助金情報は、
- 市区町村の公式ウェブサイト
- 住民課・福祉課・環境課などの窓口
で確認できます。
墓じまいで使える補助金の申請方法と注意点
墓じまいで使用できる補助金の申請には、以下のような手順が一般的です。
- 自治体の補助金制度を確認する(ネットや役所窓口)
- 必要書類を準備(改葬許可証、墓石撤去の見積書、業者の情報など)
- 工事前に申請し、承認を得る
- 墓じまい完了後、実績報告書を提出
- 補助金の受け取り
注意点としては、「工事後に申請しても補助対象にならない」ケースが多いことです。必ず工事前に申請し、承認を得てから着工するようにしましょう。また、申請時には写真や図面、契約書など多くの書類が必要となる場合もあるため、余裕を持って準備することが大切です。
墓じまいの流れに関しては、以下の記事で確認してください。

墓じまいと一緒に考える「実家じまい」
お墓を整理するタイミングで、実家じまいを検討する方も少なくありません。特に田舎や遠方にある実家を持て余している場合、「家の管理ができない」「固定資産税だけ払い続けている」といった悩みも多く聞かれます。
そうした方には、家の無料査定を活用して「売却」「解体」「賃貸」の可能性を探ることをおすすめします。
全国の不動産会社に一括で査定依頼できる『イエウール』なら、たった1分の入力で家の相場がわかります。
墓じまいと実家じまい、両方をセットで考えることで、心も暮らしもずっと軽くなるはずです。
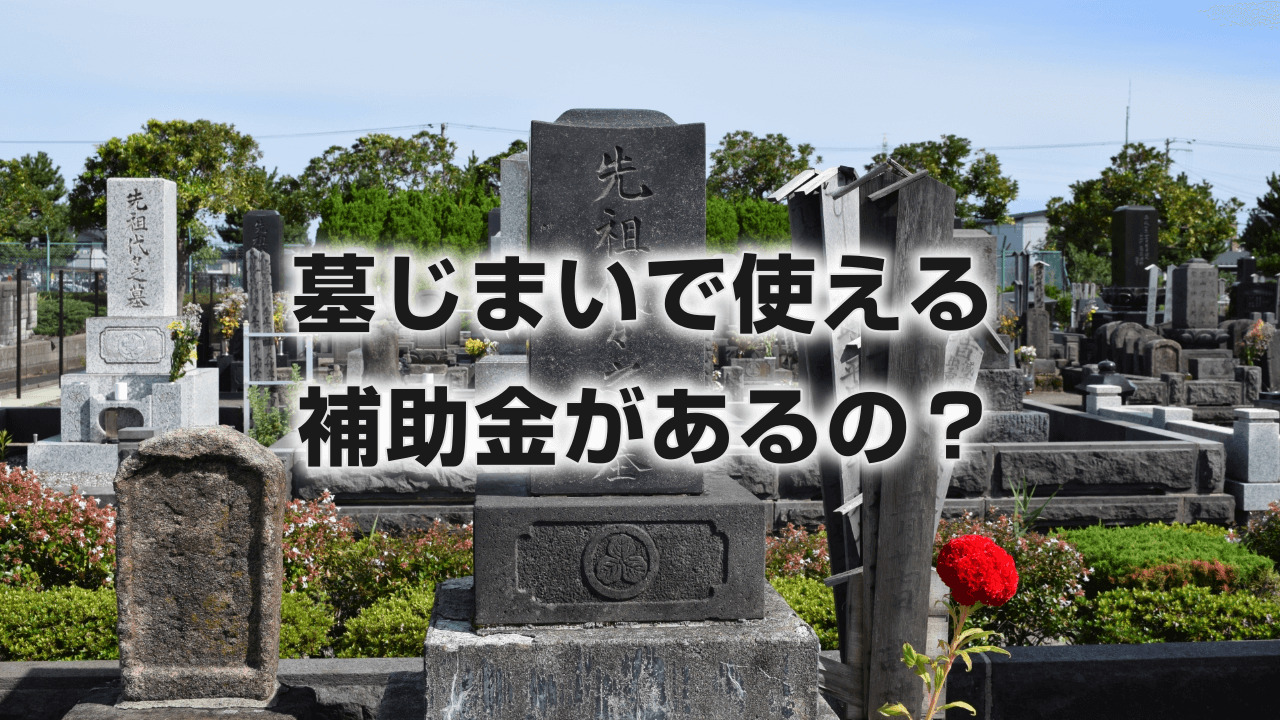



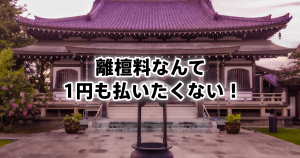
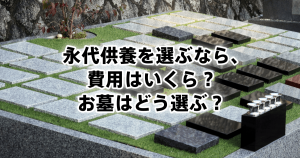

コメント